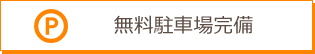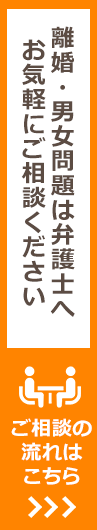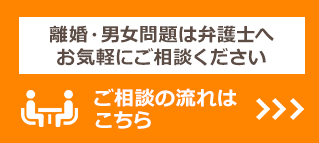弁護士法人美咲では、看護師の方からの離婚相談も多くいただいております。この記事では、看護師の方が離婚する際に問題になるケースやよく相談を受ける内容について解説します。
目次
親権について
看護師の方で病院に勤務されている場合は、夜勤や土日出勤等、不規則な勤務時間となることが多くあります。そのため、お子さんがいらっしゃる場合には「自分は親権を取得できますか」と心配になる方もいらっしゃいます。
この点、勤務時間が不規則であっても、それだけで親権の取得が困難になるわけではありません。
かりに配偶者から親権を争われた場合、裁判所が重視する点は、子の監護実績、監護能力、環境、子の意思等を総合的に考慮します。仕事の帰りが不規則であるという点をもって不利になるわけではありません。もし離婚後も同じ職場で勤務をする場合は、夜勤等の際にお子さんを親などに預けることができるといった点をフォローしていくことが考えられます。
養育費について
養育費は夫と妻の双方の収入額をもとに判断します。看護師の場合、平均的な収入よりも高額になることが多く、その分、養育費が少なくなってしまうという可能性があります。
注意が必要な方は、夜勤等が多い方です。養育費は、実務上、前年の収入資料に基づいて算定をします。例えば、令和7年に離婚協議をする場合、令和6年源泉徴収票の金額をもとに算定をするとい扱いが定着しています。そのため、昨年は夜勤等がたまたま多くて収入が多かったものの、現在は配偶者と別居をして、その分夜勤等を減らしたため、収入が大きく減少している場合です。
この場合、前年の収入をもとに養育費を算定すると、現在の収入額で計算した養育費よりも低額になってしまうリスクがあります。
このような事態を回避するためには、給与明細等を提出し、現在の収入額を証明していくことが必要です。
財産分与について
看護師の方であっても、配偶者が一般的な会社員の場合は、一般的な財産分与のケースとさほど違いはありません。
他方で、看護師の方は医師と結婚するケースが多く、配偶者が医師の場合は結婚後に築いた財産が高額になるケースがあります。そして、その財産の大半が医師である配偶者の名義になっていることが多いのではないでしょうか。
この場合、配偶者名義の財産を全て調査することが重要です。預貯金、株式、投資信託、保険、退職金、仮想通貨等、できる範囲で調査をしましょう。
また、医師である配偶者が自身で開業をしており、それが医療法人の場合は、持分が財産分与の対象となります。また、医師はMS法人(メディカルサービス法人)を保有していることが多く、この場合、同法人(株式会社や合同会社など)の株式(持分)も財産分与の対象となります。こういった法人格の持分の評価額は、決算報告書を確認したり、場合によっては税理士に直近の評価を算定してもらったりする場合もあります。
<2分の1ルールの修正>
財産分与は基本的には夫婦共有財産を2分の1ずつに清算をします。しかし、場合によってはこの2分の1ルールを修正する場合があります。
裁判所は、①「夫婦の一方が,スポーツ選手などのように,特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが,加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり,通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合など,高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を保障するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合」や、②「高額な収入の基礎となる特殊な技能が,婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成されて,婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合」には、2分の1とは異なる割合で清算することが公平であると述べています。
その上、医師の財産分与について、その財産を築いたことへの寄与の割合として、医師が6割、その配偶者を4割と判断しました(大阪高判平成26年3月13日)。
このような2分の1以外の割合は個別具体的な事情により判断が異なりますから、一概にこの裁判例が当てはまるというわけではありません。
しかし、配偶者が医師である場合、2分の1とは異なる割合での清算を主張される可能性があることは、念頭に置いた方がよいでしょう。
弁護士法人美咲にご相談ください
看護師が離婚を考える場合、上記のような法律的な問題点が多く生じる可能性がありますし、そもそも、看護師の方は忙しいことが多く、ご自身で離婚問題を対応することは大変な負担となります。まずは弁護士に相談をし、今後の見通しをつけるだけでも精神的な負担を軽減できます。
まずはお気軽にお問合せください。