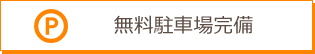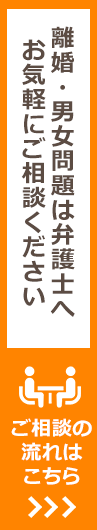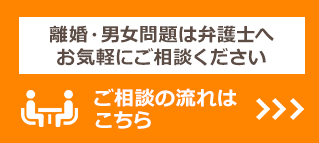~50代、60代のための離婚相談~
熟年離婚は、長年連れ添った中高年層の離婚を言いますが、厳密な定義があるわけではありません。婚姻期間が20年以上のケースを意味することが多くあります。厚生労働省の人口動態統計によれば、2022年の同居20年以上の離婚は約3万9000件となり、過去最高の件数でした。熟年離婚は決して珍しいことではないことがわかります。実際、弁護士法人美咲にも、男性女性を問わず、熟年離婚を検討されている方の相談は多く寄せられます。
この記事では、熟年離婚の原因や熟年離婚をする場合の注意点等を弁護士が解説します。
目次
熟年離婚の原因
長年連れ添った夫婦だからこそ発生する離婚原因があります。その代表的なものをご紹介します。
① 定年退職後に一緒にいる時間の増加
② 子どもが自立していないこと
③ 介護の問題
④ 不倫
それぞれ詳しく解説します。
① 定年退職後に一緒にいる時間の増加
夫婦の一方あるいはお互いが定年退職により、必然的に自宅で配偶者と一緒に過ごす時間が多くなります。
この中で、妻は夫のご飯を作る回数が増え、また、家事が増加していきます。かといって、長年一緒にいて新しい話題もありません。夫婦共通の趣味があってそれが楽しめればよいですが、そううまくいかないことも多くあります。段々と会話がなくなり、夫婦関係が悪化し、離婚に至るというケースがあります。
また、定年退職前からの不満が蓄積し、退職というタイミングで離婚を切り出すということもあります。
② 子どもが自立していること
子どもが自立しているため、離婚をすることへのハードルがかなり低くなることは現実としてあります。子が小さいときはお金の問題もありますから、なかなか離婚に踏み切れない夫婦であっても、子が大学に進学したり、就職したりして、親元を離れると、離婚をする心理的ハードルが一気に低くなり、離婚を決意しやすくなるということがあります。
③ 介護の問題
これは、義理の両親の介護、自身の両親の介護、そして配偶者の介護の問題を含みます。
昔と異なり、「妻が夫の親の介護をする」ということは当たり前ではありません。妻も自身の人生があり、また、自身の家族を支えたいという気持ちもあります。
他方で、「妻が夫の親を世話するのが当然」とうい価値観の方もいまだ多く存在します。
このようなことから、夫と妻とで価値観の対立が生じ、離婚に至るケースがあります。
④ 不倫
不倫は若い世代だけの問題ではありません。意外に思われるかもしれませんが、中高年層の不倫も多くあります。
社内での不倫、趣味などのサークルでの不倫、最近ではマッチングアプリを利用しての不倫も増加しています。
長年連れ添って信頼していた配偶者が不倫をしてしまうことで、信頼関係が一気に崩れてしまい、そのまま離婚に至るケースがあります。
財産分与に注意しましょう!
「離婚して一人で生活できるでしょうか。」
そんな経済的な不安をお持ちの方が多くいらっしゃるかと存じます。熟年離婚でとにかく注意する点は「財産分与」です。
日々の家計は全て妻(夫)に任せっきりで、収入がどれくらいなのか、どういった財産があるのか全くわからないという方もいらっしゃいますが、きちんと調査をしましょう。
調査といっても難しいことではありません。まずは、配偶者名義の預貯金通帳、証券会社から届いている定期報告書、給与明細や源泉徴収票、保険証券等をチェックしてみましょう。
財産分与でいくら取得できるかイメージが湧かない方のために、最高裁判所が公表している「令和5年司法統計年報」
をご紹介します。
全体的に婚姻期間が長くなれば長くなるほど財産分与の対象額が増加する傾向にありますが、婚姻期間が20年を超える場合、財産分与の額が1000万円を超えるケースが約23%もあります。また、婚姻期間が25年を超える場合は、財産分与の額が1000万円を超えるケースが31%に増加します。中には、2000万円を超えるケースも増えていくことがわかります。
熟年離婚を後悔しないために
①まず別居後の住まいや生活スタイルを予測する
離婚後に大切なのは、まず住まいを確保することです。住居関係費が生活費のかなりの割合を占めてしまうためです。
今の家に住み続けるのか、それとも実家に帰るのか、さらにはアパート等を借りて居住をするのか。
その上で、今後どういった生活を送っていくのかをイメージすることで、必要な生活費などを計算することが可能になります。
②財産分与の対象となる財産を調査する
財産分与の対象財産を調査することが必要です。ご自身で配偶者の財産を全て管理しているような場合は容易ですが、そうでない場合は、自身の財産と配偶者の財産をきちんと調査しましょう。通帳、保険証券、株式、投資信託、固定資産税納税通知書など、確認する資料は多くあります。
③生活費を貯蓄や財産分与から賄えるかどうか計算する
次に、財産分与で取得できる財産額の予想をしたら、自身で計算した生活費を賄えるかどうかを計算しましょう。離婚をすると、元配偶者に対して生活費を請求することはできませんから、ここは注意が必要です。
弁護士法人美咲にご相談ください
長年連れ添った配偶者との離婚は何かと大変です。まずは弁護士に相談することで、より正確な見通しを立てることができます。弁護士法人美咲では熟年離婚の案件を多数取り扱った実績があります。安心してご相談ください。