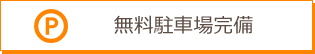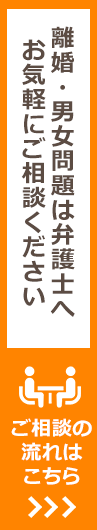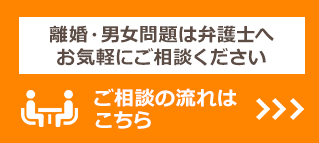日本では盆暮に実家に帰省するという風習がありますが、自分の実家に帰省する時には配偶者も一緒に帰省することが一般的です。ご家庭によっては、実家で何日も宿泊することもあるでしょう。しかし、従来は当たり前と思われていたこの風習にも変化が見られ、近年はこの帰省を巡り夫婦間で見解が対立し、夫婦仲が悪化してしまうケースもあります。
この記事ではお盆や年末年始の帰省をめぐって夫婦仲が悪化した場合のことを解説いたします。
目次
親族の不和が離婚原因となっている件数
離婚を決意した理由として義父母との不和等を挙げる人は意外と多くいらっしゃいます。最高裁判所が公表する令和6年司法統計年報(家事編)が離婚調停の申立ての理由となっている件数は、妻からの離婚調停の申立て(申立て件数総数43 033件)のうち2358件(全体の約5%)を占めます。これは妻側から離婚を求める理由の10位にランクインしています。
夫からの離婚調停申立て(総数1万5396件)のうち1699件(全体の11%)が「家族親族との折り合いが悪い」という理由を挙げているのです。夫からの離婚を求める離婚原因の第5位にランクインしているのです。少し意外かもしれませんが、女性よりも男性の方が親族との折り合いが悪いことから離婚を決意していることがわかります。
夫も妻も、夫婦関係のみならず、義父母や親族との関係に悩んでいるケースが多いと言えます。
実際の相談であった親族トラブルエピソード
弁護士法人美咲に寄せられる離婚相談の中でも、義父母や親族との折り合いが悪いことを離婚の理由に挙げる方がいらっしゃいます。そこで、実際にご相談のあったエピソードをご紹介いたします。
夫が田舎の出身で、実家に帰ると親族全員が集まり宴会が始まります。義母や私は料理などの準備に駆り出され、会ったこともないような夫の親族にお酌するなど、本当に嫌でした。夫は私が料理の準備をしたりすることを当たり前だと思っており、私が夫の帰省についていきたくないと言ったら、激怒しました(40代・女性)
夫の実家がお寺のため、お盆は檀家さんのために大量の料理を作らなければなりませんでした。私が早朝から支度をしていることについて、夫は何も思わないようで、腹立たしかったです(60代・女性)。
妻の母が、プライベートに口を出してくる人で、私の収入のことや子供のことにあれこれ言ってくることが苦痛でした。かといってお金を出してくれるわけではなく、なんでここまで言われなきゃいけないのだろうと思っていました(40代・男性)。
実家への帰省の頻度や帰省したときに行わなければならないその家族や地域特有の義務、義父母との関わり方、義父母からのプライベート(子育てを含む。)への干渉などが多い印象です。
義父母との不和を理由に離婚できる?
義父母との関係悪化を理由として離婚請求する場合、夫(妻)が離婚に応じていない場合、その状態が法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当している必要があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」は原則として夫婦関係に関する事情が想定されていると解され、義父母との不和が直ちに該当するわけではありません。
しかし、夫婦は婚姻関係を良好に維持するためにお互いに力を尽くす義務を負っています。それにも関わらず、義父母との不和が生じていることを認識していながら、それを何も対処しようとしない行動は、共同生活を営もうとするために力を尽くしていないと認定される場合があります。
実際に、義父母との不和が生じている中で、なんら夫(妻)が対応しなかったことから、夫婦関係が破綻に至ったという事情がある場合に、離婚請求を認めている裁判例もあります。いくつか裁判例をご紹介いたします。
東京地裁平成6年9月28日
サラリーマン家庭で育った妻と、鰻屋を家族総出で営む夫の家庭環境が大きく異なり、同居生活において原告が順応できなかったこと、鰻屋の同居家族である姑や長姉(小姑)から、妻の私生活(部屋への無断侵入、クーラーや洗剤の使用方法など)にまで細かく干渉され、妻は精神的に不安定になったこと、妻が鰻屋の仕事に従事したにもかかわらず、姑から月にわずか3万円の小遣いしか与えられず、経済的な独立性が確保されなかったこと、妻が家族との軋轢や精神的な苦痛を夫に訴えても、夫は真剣に取り合わなかったこと等から妻が離婚を求めたところ、裁判所は、夫婦間の価値観の大きな隔たりと、それから生じる具体的な生活上の軋轢に対し、被告が適切な対応をとらなかった結果、原告の信頼が完全に失われ、夫婦関係が回復不可能なまでに破綻したと認定し、離婚請求が認められました。
東京高裁平成元年5月11日判タ739号197頁
妻は、夫と夫の母(義母)と同居していたところ、義母との関係が悪化し、妻が自宅を出て別居を開始しました。別居期間が長期になったことから夫が妻に対して離婚請求をしました。裁判所は夫婦の別居期間が約10年経過していたものの、「X(夫)は、A(夫の母)のY(妻)に対する嫁いびり延いては追い出しの策動に加担し、これを遂行したとの非難を免れえず、婚姻破綻につき専ら(ここでは主としての意)責任を有する者として、本訴は有責配偶者の離婚請求と断ぜざるを得ない」として、夫からの離婚請求を認めませんでした。これは、嫁いびりなどに加担したことが離婚原因に至った大きな理由であるとして、夫側に責任があるとし、有責配偶者からの離婚請求を認めないと判断をしたものです。
お盆離婚をする場合の留意点
お盆の帰省を前にして、また、帰省後に離婚を決意するとして、離婚をするにはどういった点に注意しなければならないかを説明します。
タイミング
離婚に適切なタイミングというのはケースバイケースなので一概には言えませんが、お子さんがいる場合、8月は離婚するタイミングとして良いと言えます。なぜなら、夏休み期間であるため、自宅から引っ越して別居するにあたり、お子さんが学校を休まずに手続きができるメリットがあるからです。
生活費等の確保(婚姻費用、養育費)
別居をする場合は生活費をきちんと払ってもらう必要があります。離婚するまでの生活費等を婚姻費用、離婚後のお子さんの生活費等を養育費と言いますが、いずれも双方の収入をもとに金額を決めることが多いです。実務上は、転職などの事情がなければ、直近の源泉徴収票をもとに決めることが多いです。相手方の給与明細や源泉徴収票を見たことがないという夫婦も多くいますが、別居するタイミングで自宅にないかどうかを確認することをお勧めいたします。
財産分与に向けての準備
離婚をする場合は財産分与に向けた準備をきちんと行いましょう。特に通帳、保険証券、有価証券(株、投資信託など)、積立、仮想通貨など、自宅になんらかの資料が置いてあることが多く、こういった資料は別居後に確認することが困難ですから、別居前に確認するようにしましょう。
親族との関係で離婚を考えたら…弁護士に相談するとできること
義父母や親族との不和で悩んでいる場合、気持ちが前向きにならず、毎日が苦しい思いをしていることでしょう。弁護士に相談することで、何が問題なのかを整理し、どういった対応ができるのかを明確にすることで、次にステップに目を向けることができます。
まずは弁護士法人美咲にお気軽にお問い合わせください。